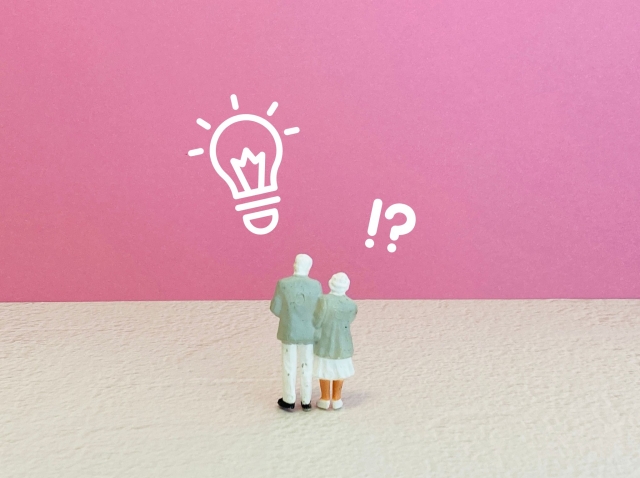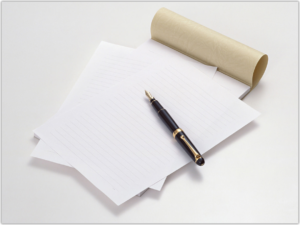遺言書についてお客さまからよくいただくご質問をご紹介いたします。
 遺言書は一度書いたら訂正はできない?
遺言書は一度書いたら訂正はできない?
![]() 遺言書はいつでも訂正できます。
遺言書はいつでも訂正できます。
新たに作り直した際は、作成年月日の新しいものが有効になります。
 配偶者(夫又は妻)に家を残したい
配偶者(夫又は妻)に家を残したい
![]() 平成30年7月13日の相続法改正によって、遺言書で配偶者に居住建物の居住権を取得させることができるようになりました。遺言書ではなくても遺産分割協議においても選択出来るようになりました。また、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方に居住不動産を遺贈や贈与した場合は、相続財産として持ち戻しをしないことになりました。
平成30年7月13日の相続法改正によって、遺言書で配偶者に居住建物の居住権を取得させることができるようになりました。遺言書ではなくても遺産分割協議においても選択出来るようになりました。また、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方に居住不動産を遺贈や贈与した場合は、相続財産として持ち戻しをしないことになりました。
つまり、遺贈や贈与された居住用不動産は相続の対象とならず、配偶者が取得できるようになりました。
 自分の亡き後、親代わりになって育ててきた孫(未成年)が心配
自分の亡き後、親代わりになって育ててきた孫(未成年)が心配
![]() 遺言書で未成年後見人を指定しておきましょう。
遺言書で未成年後見人を指定しておきましょう。
未成年後見人とは、親代わりとなって未成年者の教育や財産管理などを務める人のことです。
未成年後見人に指定する人には、事前に依頼し、了承を得ましょう。
 家族に代筆してもらって遺言書を書くことができる?
家族に代筆してもらって遺言書を書くことができる?
![]() できません。
できません。
ただし、平成30年7月13日の相続法の改正により、財産目録はパソコンで作成しても
良いことになりました。また、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として
添付できるようになりました。
 認知したい子がいる
認知したい子がいる
![]() 遺言書で認知できます。
遺言書で認知できます。
遺言で認知をする場合は必ず遺言執行者を指定しましょう。
 亡くなった長男の嫁に財産を残したい
亡くなった長男の嫁に財産を残したい
![]() 遺言書で指定しないとできません。
遺言書で指定しないとできません。
息子の妻には相続権はありません。遺言書で指定しましょう。
他の相続人の遺留分(法律で守られている最低限の相続分)を侵害しないよう注意が必要です。
 先祖代々のお墓や祭祀の継承が心配だ
先祖代々のお墓や祭祀の継承が心配だ
![]() 遺言書で指定しましょう。
遺言書で指定しましょう。
祭祀財産の承継者は責任や費用の負担がかかります。
そのことを考慮して、相続分を増やすなどの配慮が必要です。
 公正証書遺言の証人を親族に頼みたい
公正証書遺言の証人を親族に頼みたい
![]() 利害関係人は証人になれません。
利害関係人は証人になれません。
遺言書に名前の出てこない第三者に頼みましょう。
 夫婦で一緒の遺言書を作りたい
夫婦で一緒の遺言書を作りたい
![]() できません。
できません。
遺言書は個人のものです。
夫婦であっても、別々の遺言書を作りましょう。
 遺言書を見つけたらすぐに開封しても良い?
遺言書を見つけたらすぐに開封しても良い?
![]() 開封してはいけません。
開封してはいけません。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。
故人が自書した遺言書だということを証明してもらうための手続きで
違反をすると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。